杉山吉成(八兵衛)は、石田三成の次男・石田重成(杉山源吾)の長男です。
弘前藩・津軽氏に仕え、シャクシャインの戦いでは侍大将として活躍しています。
「早道之者」という忍者集団の結成にも関わったと見られ、津軽杉山家と忍者についても書いています。
杉山吉成は石田三成の孫
杉山吉成(八兵衛)の生年は定かではありませんが、慶長15年(1610年)頃、誕生したと見られています。
父は石田三成の次男・石田重成(杉山源吾)で、長男として生まれています。
石田三成の孫に当たる人物です。
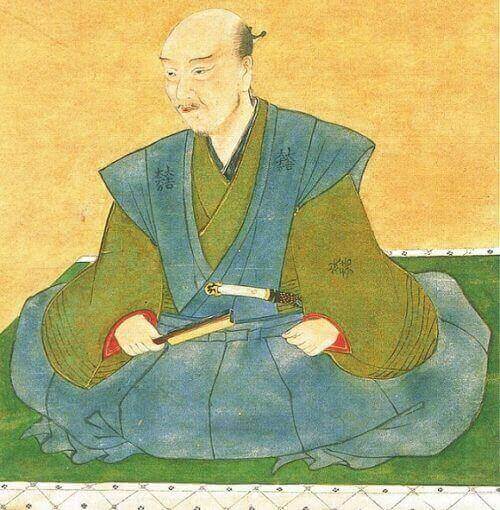
母はWikipediaによると岩田氏娘・瑞岳院となっていますが、この方は石田三成の生母とされている方です。
石田三成の子供達の家系図は、徳川の世を憚ってか、故意に謝ったことが書かれているそうで、情報が錯綜しているのかもしれません。
杉山吉成の通称は八兵衛ですが、石田三成の三人の娘は、八兵衛吉成(杉山吉成)の姉とする記録もあるそうです。
杉山吉成(八兵衛)の生母は、石田重成の正室・朽木氏娘であるとと伝わります。
吉成の父・石田重成は、豊臣秀頼の小姓を務めた人物です。
慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いが起きた時、石田重成は大坂にいました。
石田三成は関ヶ原の戦いで大敗し、居城の佐和山城も落城します。

佐和山城が落とされたことを知った石田重成は、三成が烏帽子親を務めるなど懇意にしていた津軽信建の助けで津軽へ逃げ延びています。
このような経緯で父が陸奥国津軽に逃れた10年程後に、杉山吉成は生まれたことになります。
杉山吉成 津軽家に仕える
杉山吉成(八兵衛)は、陸奥国弘前藩2代藩主・津軽信枚に仕えています。
津軽信枚に吉成の叔母にあたる辰姫(三成三女)が嫁いでいた縁でしょうか、杉山吉成は藩主・津軽信枚の娘・子々(子之姫)を娶っています。

また、弘前藩初代藩主・津軽為信(信枚の父)の時代、豊臣秀吉によって滅ぼされる可能性があったところを、三成の取り成しで助けられた過去があります。
そのことから津軽家は、石田三成に恩義を感じていたとされます。
石田三成の縁者に良くしてくれる一因であると思われます。
寛永8年(1631年)、藩主・津軽信枚が没すると、 津軽信義が3代目藩主になります。

津軽信義は辰姫(三成三女)の子供ですので、杉山吉成(八兵衛)の従兄弟ということになります。
寛永21年(1644年)には1300石を拝領し、弘前藩(津軽家)の軍事組織を担う重臣になります。
その後の杉山家当主は、藩の重臣として幕末まで続くことになります。
杉山吉成とシャクシャインの戦い
明暦2年(1656年)、津軽信義の長男・津軽信政(三成の曾孫)が家督を継いで、藩主になっています。
寛文9年(1669年)、シャクシャインの戦いが起きます。
元は蝦夷地のアイヌ民族同士の争いでしたが、誤報に加えアイヌ民族の生活を圧迫した松前藩に対し、敵対感情を強めます。
アイヌ一部族の首長・シャクシャインは、松前藩への戦いを呼びかけ、一斉蜂起が行われました。
松前藩は出陣すると共に、幕府に援軍や支援を要請しています。
幕府は弘前藩の津軽氏、盛岡藩の南部氏、秋田藩の佐竹氏に蝦夷地に出陣準備の命令を出しています。
幕府や松前藩から要請を受けた弘前藩の動きは早く、積極的だったと伝わります。
津軽勢は3000人の兵を3隊に分けており、杉山吉成(八兵衛)は一番隊侍大将として700人の藩兵を率いて松前に向けて出港しています。
杉山吉成(八兵衛)ら津軽勢は、浄土真宗・専念寺を本陣とし、松前城下の警備、後方支援の体制を整えています。
そして、松前で待機しながら弘前藩に戻るまでの間、松前藩士から戦況を聞いて弘前藩や幕府に報告しています。
また、アイヌ民族側の言い分も自身で調べたそうです。
松前藩は津軽藩、南部藩などから鉄砲を借り入れ、鉄炮の威力で松前藩が優位となり和議を結んでいます。
ですが、和睦の席でシャクシャインは亡き者にされ、指導者を失った蜂起軍は降伏しています。

杉山吉成(八兵衛)は、戦場の最前線視察をし進軍を希望していますが、松前藩から拒否され、あまり戦火を交えず、戦を終えたようです。
江戸城に登城
弘前に帰陣した杉山吉成(八兵衛)は、幕府に報告の為、藩主・津軽信政の書状を持って江戸に上がります。
幕閣に面会した杉山吉成(八兵衛)は、シャクシャインの戦いの報告、扶持米のお礼を藩主に代わって述べています。
杉山吉成(八兵衛)は、老中らに働きを評価され、酒肴を賜り、歓談を行っています。
杉山吉成に対して幕府は好意的に接してくれています。
弘前藩4代藩主・津軽信政(三成曾孫)の正室は、4代将軍家綱の従妹である不卯姫です。
この関係から、将軍家綱の時代は津軽家と良好な関係であったようです。
また、杉山吉成(八兵衛)の活躍は弘前藩としての評価にも繋がります。
喜んだ藩主・津軽信政は、杉山吉成(八兵衛)の留守中に、吉成の息子・吉煕に白鳥一羽、酒一荷、昆布一箱などの品を贈っています。
その後、弘前に戻った杉山吉成(八兵衛)は、小袖三箱、肴三種、酒二荷を賜っています。
寛文12年(1672年)3月30日、杉山吉成(八兵衛)は、没しています。
生年慶長15年(1610年)であれば、享年63歳です。
津軽杉山家と忍者
近年、忍者屋敷に石田三成の子孫が住んでいたことがわかり、ニュースになりましたので紹介させていただきます。
先に述べたように杉山吉成(八兵衛)は、シャクシャインの戦いに侍大将として参じています。
シャクシャインの戦い以降、弘前藩は蝦夷地に対する最前線基地という位置付けになっています。
松前藩の統治力を危ぶんだのか、シャクシャインの戦いから約4年後、中川小隼人など甲賀忍者を召し抱え、「早道之者」(はやみちのもの)という忍者集団を結成させたようです。
「早道之者」結成の前年に、杉山吉成(八兵衛)は没しています。
しかし、「戦と諜報」のトップを務めた杉山吉成(八兵衛)の遺志であったと見られています。
「早道之者」は、弘前藩と松前藩の商取引の際には立ち合い、蝦夷地に渡り情報収集を行っています。
後に、ロシア船が蝦夷地に来航すると、「早道之者」が警備したそうです。
平成28年(2016年)秋頃、青森県弘前市内で忍者屋敷が見つかっています。
平成29年(2017年)夏頃のニュースで調査の結果、忍者屋敷は杉山家の末裔・白川孫十郎氏が住んでいたそうです。
この忍者屋敷は、「三成や忍者ゆかりの地を巡るツアー」という観光スポットとして町興しの期待もある様子です。
三成の祖母は甲賀の多喜家出身
石田正継の生母(三成の祖母)は、甲賀の多喜家出身で、多喜資盛の娘とする説があります。
甲賀の多喜家といえば、甲賀流忍術の中心となった甲賀五十三家を連想します。
天正11年(1583年)、賤ヶ岳の戦いが起きた際、石田三成は諜報活動を行っており、忍者を連想させます。
石田三成と忍者には縁があるのではないか、研究が進んで欲しいと思っています。
また、杉山家の伝承によると、関ヶ原の戦いより前に、秀頼から「杉山の郷」を拝領していたと伝わるそうです。
それは、現在の滋賀県甲賀郡信楽町大字杉山に当たるようです。
三成次男が杉山性を称したのは、「杉山の郷」が理由の一つという可能性もあるでしょうか?
 かおりん
かおりん 戦国時代ランキング
戦国時代ランキング


コメント