豊臣秀吉の小田原征伐の中で、最後まで抵抗したのは、難攻不落の忍城でした。
石田三成が水攻めをしたことで知られる忍城の戦いについて書いています。
忍城の戦いに至る経緯
忍城の戦いは、豊臣秀吉の天下統一の総仕上げである小田原征伐の一環です。
小田原城の周囲の城を巻き込ん戦で、最後まで抵抗を続けた難攻不落の忍城を舞台にした戦いです。
まず小田原征伐や忍城の戦い、に至る経緯を書きます。
天正16年(1588年)4月、豊臣秀吉は、自身の邸宅でもある聚楽第に後陽成天皇を迎えて饗応します。
豊臣秀吉は、既に徳川家康や織田信雄に忠誠を誓わせており、事実上の天下人になっていました。

しかし、関東最大規模の後北条氏(小田原北条氏)、後北条氏の同盟相手である伊達政宗は、秀吉に主従していませんでした。
後北条家の当主は、北条氏直という人物で、妻は徳川家康の次女・督姫です。
北条氏直と徳川家康は同盟関係にありました。
徳川家康は、北条氏直とその父・氏政に起請文を遣わして、秀吉に主従するよう促します。
もし従わなけらば、督姫と離縁の上、同盟関係を解消するという家康からの最後通告を受け、北条氏直は秀吉の軍門に降る決意をします。
北条氏直の叔父・氏規を名代として上洛させて、秀吉に恭順の意を示します。
しかし、天正17年(1589年)11月、後北条氏の家臣・猪俣邦憲(いのまた くにのり)が、真田昌幸の名胡桃城(なぐるみじょう)を奪い取ってしまいます。
豊臣秀吉は、大名間の争いを禁じる「惣無事令」を発令していた為、小田原征伐の大義名分を与えることになりました。
その後、豊臣秀吉の最後通告にも関わらず、弁明と徳川家康に取り成しを頼むばかりの後北条氏の態度を受けて、秀吉は後北条氏を征伐する意向を示します。
忍城の戦い
忍城の城主は、後北条氏に帰参して家臣になっていた成田氏長でした。
しかし、成田氏長は小田原征伐の報を受けて小田原城に籠城していた為、一門衆で家臣である成田泰季に城代を任せます。
忍城には、成田泰季の嫡男・成田長親、成田氏長の娘・甲斐姫など約2千人が籠城することになりました。
石田三成を総大将にして、大谷吉継、長束正家など大軍が忍城に攻撃を仕掛けますが、容易に落とすことは出来ません。
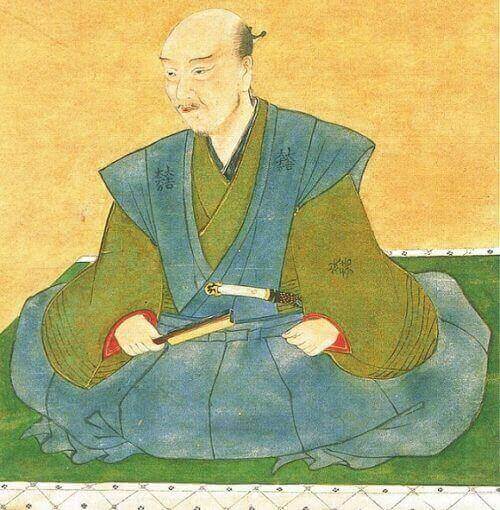
この時の軍勢は、分かりませんが、忍城攻めの豊臣軍の総勢は2万~5万人と云われています。
北を利根川、南を荒川に挟まれた忍城は、河川や沼を堀として利用した堅城であり、天然の要害に守られていました。
真田昌幸、浅野長政なども忍城攻めに加わりますが、豊臣軍は攻めあぐねることになります。
忍城水攻めの下知
その後、豊臣秀吉から忍城を水攻めにするよう命じられます。
忍城の周囲を水で囲んで兵糧攻めにしようとする作戦です。
水攻めと言えば、豊臣秀吉が行った備中高松城の水攻めが知られていますが、高松城の水攻めを成功させたことで、秀吉の名を天下に轟かす一因になっています。
石田三成は、丸墓山古墳に本陣を構え、忍城を包囲します。

当時の書状によると、石田三成は水攻めに反対であり、その旨秀吉に進言しています。
忍城の回りは平丹な関東平野で、高低差が無い為、水は溜められないと見立てたものと思われます。
『成田記』によると、三成以外の武将も忍城の水攻めに反対であったそうですが、秀吉は改めて水攻めを命じ、三成に細かな指示をしています。
また、具体的な戦術については、浅野長政の指示を仰いでいます。
浅野長政は、三成の先輩に当たる人物で、忍城の戦い当時の秀吉書状に、浅野長政に相談するよう書かれています。
忍城を囲む堤防
その後、僅かな地形の高低差を見つけた石田三成は、高低差がわずかな分、長い堤防を築いて十分な水を確保しようと考えたようです。
当時、田舎町であった忍城周辺で、十分な人夫や資材を調達する必要に迫られます。
そこで、石田三成は、昼は米一升と永楽銭六十文、夜は米一升と永楽銭百文という破格の待遇を工事をする地元の民に与えます。
あまりの待遇に、遠くの国からも人夫が押し寄せ、10万人もの人が集まりました。
昼夜問わず工事を行うことで、4、5日という猛スピードで堤防を完成させています。
忍城を中心に南方に半円形の全長28kmもある堤防であったと云われ、石田堤として一部現存しています。

水攻め決行
その後、利根川、荒川の水を引き入れて忍城の水攻めを決行します。
しかし、忍城の本丸を沈められず、まるで城が浮いているように見えたため、「忍の浮き城」という異名がついています。
その後、梅雨時期であったこともあり、降り続く豪雨により、忍城の本丸まで沈みそうになります。
夜中に忍城をコッソリ抜けた城を守備する侍により、堤の二箇所を破壊されます。
決壊した堤から、水が溢れだして、豊臣軍約270人を失います。
忍城の戦いから一カ月が経過しましたが、忍城を落とせません。
更に豊臣軍に援軍が到着し、攻城戦をしかけますが、やはり落城しませんでした。
小田原城は既に降伏し、残っているのは忍城だけという状況です。
忍城の開城
小田原城に籠城していた忍城の城主・成田氏長は、秀吉に促され、忍城に降伏を勧めます。
成田氏長の呼びかけに応じて、ついに忍城は開城することになりました。

忍城の戦いにより、石田三成は戦下手の烙印を押されたそうです。
筆者の所感になりますが、天下統一目前の豊臣軍は、大軍を擁しており、最終的に敗北は考えずらい状況だったと思います。
豊臣秀吉が水攻めを命じたのは、効果的だからというより、世間に与えるインパクトが大きいからではないかと考えます。
当時、天下を掌握しつつあった秀吉の軍門に降った諸将の中には、心から心腹していない者もいると思われます。
その為、豊臣軍の強さを見せつける必要があったと考えます。
小田原征伐は、豊臣秀吉の天下統一の総仕上げであるため、派手なパフォーマンスを求めていたのではないでしょうか。



コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 忍城攻撃の主将は石田三成ですが、具体的な戦術については浅野長政、木村重茲に指示を仰いでいます。 […]